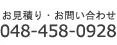冷蔵庫が無かった時代の水の活用方法
2025年1月


新しい年になりました!今年もよろしくお願いします。

よろしくお願いします!

年末年始は冷蔵庫が食材でいっぱいになりがち!なんて言われているよね。
僕の家もそうだったんだけど、ふと「冷蔵庫が無かった時代の食材保存方法」が気になったので調べてみたよ。

そもそも冷蔵庫の歴史だけど、普及率が96%に達したのは1975年と言われているよ。
長い人類史の中で「冷蔵庫が当たり前の暮らし」はまだ50年にも満たないんだ。
冷蔵庫が無かった時代はいつ?
普及率が96%に達したのは1975年(昭和50年)とされている為、本記事ではそれ以前を指します。

意外と最近の話に感じるね!

確かにね。
さて、当時食材保存する為に使われていた物を調べたらまずは「生簀」(いけす)が出てきたよ。

生簀って言うと、たまに海鮮料理屋さんで魚が泳いでいる水槽のような物?

あれも生簀なんだけど、今回は漁をした時にその場で保存するものを指すよ。
千葉県で見た生簀を紹介するから、見てもらった方が早いかもしれない。



岩礁に穴が開いてる...?

驚くことにこの岩礁自体が生簀だよ!
これは千葉県富津市で見る事ができるよ。
入口の高さはも奥行も2.5~3メートルくらいありそうだったなぁ。

技術が発展する前はこのような自然の物を利用した方法が使われていたというわけじゃな。
これはこれで興味深いけど、普通の家庭で同じ事をするのは難しいよね?
各家庭ではどうしていたんじゃ?

家庭では湧水や井戸水で食品を保冷する事で鮮度を保っていた事もあったそうだよ。
湧水や井戸水はほとんどの場合殺菌されていないからそのまま食べたりはしなかっただろうけど。


冷蔵庫が誕生する前、食材をそのまま保存する事が難しい環境では「水」が食を支えていたんだね。

そういう事になるね!どの時代の暮らしを切り取っても水が関係してくる事にいよいよ驚かなくなってる自分がいるよ。
余談だけど、このような当時の環境が「台所」の位置にも深く影響していたという事がわかったよ。

一体どういう事?

実は当時、台所は北側に配置されている事が多かったんだ。

その理由が、食材が太陽の影響を受けにくい家の北側に保管されていたので、自然と台所も北側に配置されるようになったからなんだって。諸説あるようだけどね。

へぇ~!!
食品保存の難しさが台所の位置にまで影響していたんだね。

とまぁ少し話が逸れたけど、"昔の食品保存には水が活躍していた"って事だね。
その他に塩漬け、干物、燻製といった加工保存が食を支えていた事は言うまでもないけれど、改めて僕たちは水と共に生きているんだなと実感したよ。

改めて「水」と今ある「設備環境」を大切にしなきゃいけないと思うね。

この実感を日々の業務に活かし、今年も水と空気の設備管理に邁進していくよ!
それでは、本年もよろしくお願いします!